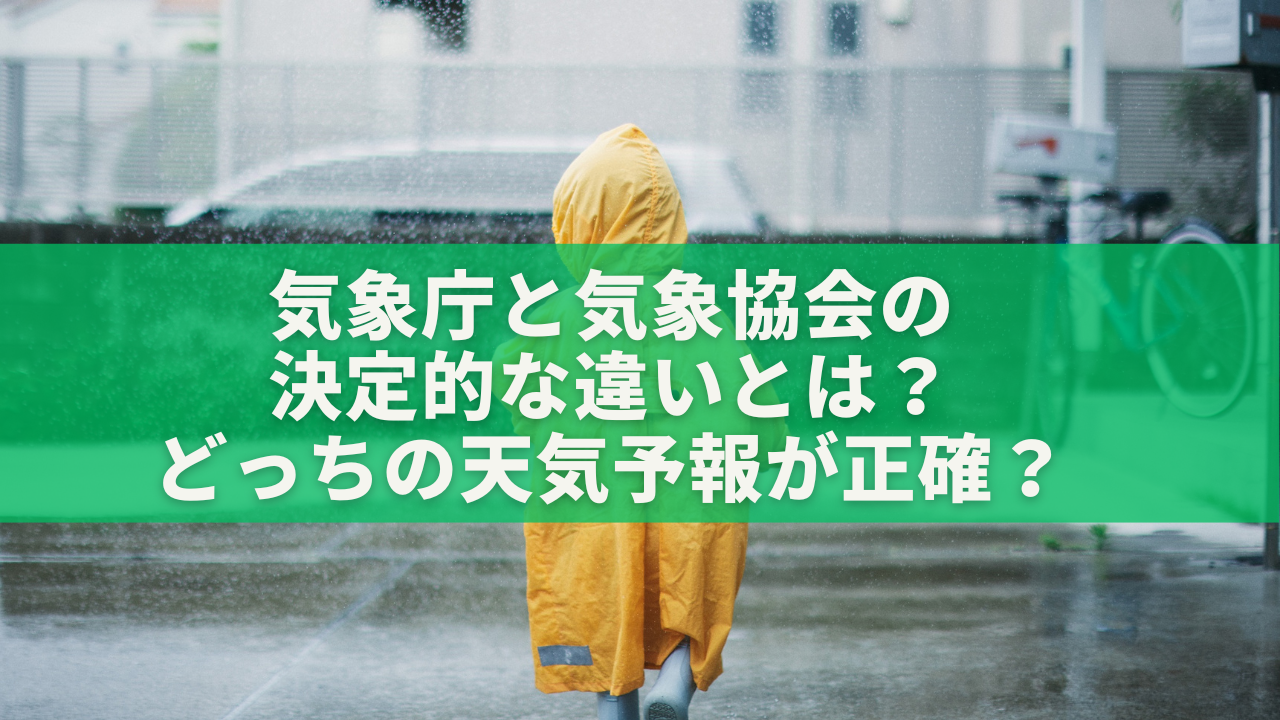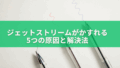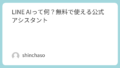日々の生活に欠かせない天気予報。しかし「気象庁と日本気象協会の予報はどちらが正確なのか?」と疑問を持つ人は少なくありません。
結論から言えば、防災や災害対応には気象庁の公式発表が最も信頼でき、日常生活やレジャーに活かすなら日本気象協会の情報が使いやすいというのが実情です。両者は目的や役割が異なるため、「どちらが絶対に正しい」というよりも、状況に応じて適切に使い分けることが重要です。
本記事では、気象庁と日本気象協会の組織的な違いから、データの収集体制、予報精度、提供サービス、さらには気象予報士や最新技術まで徹底的に比較します。違いを知ることで、自分に最も合った天気予報の活用法が見つかるはずです。
気象庁と日本気象協会の違いとは?基本概要を徹底比較

気象庁と日本気象協会は、いずれも「天気予報」を提供する存在として多くの人に知られていますが、その立ち位置や役割には大きな違いがあります。
両者の違いを理解することは、どの情報をどのシーンで活用すべきかを判断するうえで非常に重要です。ここでは、両者の成り立ちや性格、組織的な位置づけなどを詳しく見ていきましょう。
気象庁は国が運営する公的機関であり、主な使命は国民の生命と財産を守ることにあります。災害対策や国の政策決定に直結する情報を扱うため、予報内容は極めて慎重で、中立性・正確性が最優先されます。
一方で日本気象協会は財団法人という形をとる民間組織で、気象庁のデータをもとにしつつも、より生活者に寄り添った情報やサービス展開を行う点に特徴があります。テレビやラジオ、アプリなど、身近な媒体を通じて私たちに届く「わかりやすい天気情報」の多くは、この協会によって支えられています。
さらに比較対象としてよく挙げられるのが、株式会社ウェザーニューズなどの完全民間企業です。これらは利益追求を目的としつつも、独自の観測網やAI技術を積極的に導入して差別化を図っています。
つまり、「国家の防災インフラを支える気象庁」「公益性を意識しながら民間視点で情報発信を行う日本気象協会」「収益モデルを持ちながら最新技術を駆使する民間企業」という三者の構図で、日本の気象情報提供は成り立っているのです。
気象庁:国土交通省の行政機関としての役割と特徴
気象庁は日本の国家機関で、国土交通省の外局に位置づけられています。その活動範囲は非常に広く、日常的な天気予報や注意報の発表にとどまらず、地震や津波、火山噴火といった自然災害に関する観測・解析・速報の発信など、防災の最前線を担っています。
また、航空や海運といった交通インフラの安全確保、農業や漁業など産業分野への気象データ提供も重要な業務です。さらに、スーパーコンピュータを用いた数値予報モデルの開発や気象衛星「ひまわり」の運用など、科学技術的な側面でも世界的に高い水準を維持しています。
これらの活動はすべて「公共の安全確保」を第一にしており、利益追求を目的としない点が最大の特徴です。国家的使命を持つ公的予報機関としての責任感が、気象庁の情報には強い信頼性を与えています。
日本気象協会:財団法人・民間組織としての業務内容
一方の日本気象協会(JWA)は、民間の非営利財団法人として設立され、公共性と民間ならではの柔軟性を併せ持つ存在です。
気象庁から提供される膨大な観測データを基に独自の解析やモデルを組み合わせ、テレビ、ラジオ、新聞、Webメディア、スマホアプリなど多様なチャネルで天気予報を発信しています。
特に公式サイト「tenki.jp」やスマホアプリは一般消費者にとって身近な情報源となっており、洗濯指数、紫外線指数、熱中症予防指数など生活に密着したコンテンツを数多く提供しています。
さらに、自治体や企業と連携した防災情報の提供、観光やイベントに特化したレジャー予報、教育活動や気象講座など、業務範囲は多岐にわたります。
生活者の視点に立った分かりやすい表現や、タイムリーな更新が重視されており、使いやすさと実用性を兼ね備えている点が日本気象協会の大きな強みといえます。
ウェザーニューズ・他民間気象会社との違い
ウェザーニューズのような株式会社と違い、日本気象協会は非営利組織であることが大きな違いです。営利企業であるウェザーニューズは、世界中に独自の観測機器や船舶・航空機からの気象データを収集する仕組みを持ち、さらにAIやクラウドシステムを活用した独立型予報を強みとしています。
たとえば、一般向けのスマホアプリに加えて、航空会社や海運会社、農業分野など産業向けの有料サービスを幅広く展開しており、収益モデルの多様化が進んでいます。こうした取り組みは民間の中でも最先端であり、スピード感ある更新やピンポイント精度の高さに定評があります。
一方で日本気象協会は、公的性格を持つ情報発信を重視しており、社会全体の安心・安全を目的としたサービスが中心です。広告収入やアプリ提供などは行っているものの、あくまで公益的な性格を優先しており、気象庁データを基盤とした信頼性重視のスタンスを崩していません。
結果として、営利を優先するウェザーニューズと、公益性を重んじる日本気象協会では、同じ「天気予報」を扱っていても発信の姿勢や提供サービスの方向性に大きな差が見られるのです。
天気予報システムとデータ収集体制の差

気象庁と日本気象協会では、観測データの収集方法や予報モデルの活用体制に大きな違いがあります。気象庁は全国に配置された観測網や気象衛星を通じて、基礎となる膨大なデータを自前で収集・解析します。
このデータには気温、降水量、風速、湿度などの基本情報だけでなく、地上・海上・上空での詳細な観測が含まれ、グローバルな予報モデルの精度向上にも役立っています。
一方、日本気象協会は気象庁の提供するデータを土台としながらも、独自の解析技術や提携先の観測システムを組み合わせ、地域性や利便性を高めています。
たとえば観光地や都市部の気象条件をより細かく反映させ、生活者や企業にとって実用的な予報を可能にしています。両者の違いを理解することで、「どの予報を参考にするのがよいか」を判断しやすくなります。
観測・予報に使うデータやシステムの違い(気象庁 vs 日本気象協会)
気象庁は自前の観測システム(アメダス、気象衛星ひまわり、気象レーダーなど)を全国規模で運用し、膨大な観測データを数値予報モデルへ投入しています。これにより数時間先から1週間先までの天気を推定することが可能で、突発的な豪雨や台風進路の予測にも活用されます。
また、データは逐次更新され、災害発生時には特別解析も行われます。一方、日本気象協会はこうした気象庁のデータを基盤としつつ、独自の統計モデルや地域特化型のアルゴリズムを組み合わせて再解析・再予測を行います。
さらに、利用者のニーズに応じて指数化した情報(洗濯・紫外線・熱中症リスクなど)を生成し、暮らしに直結する形で発信する点に強みがあります。
全国各地の観測地点とデータ連携
気象庁は全国に1300以上の気象観測所を持ち、気温・降水量・風速などをリアルタイムに収集しています。これらの観測所は都市部だけでなく山岳地帯や離島など幅広い地域に設置され、全国規模で均質かつ統一されたデータを提供できるという強みがあります。
観測網にはアメダス(地域気象観測システム)も含まれ、1時間ごとに降水や気温の変化を細かく把握できる仕組みが整っています。こうしたシステムは防災や研究用途でも欠かせない基盤となっています。
日本気象協会は、気象庁から提供される公式観測情報に加えて、自治体や民間企業と提携して独自の観測網を展開しています。学校や観光地、商業施設、高速道路のサービスエリアなどに設置された小型観測機器からもデータを収集し、地域特性を反映させた分析を行っています。
これにより町丁目単位に近いきめ細やかな情報提供が可能となり、農業や観光業、イベント運営など特定の産業にも役立つサービスを実現しています。さらに、収集データはアプリやWebを通じてユーザーに提供されるだけでなく、研究機関や自治体と共有され、地域防災計画の改善や教育活動にも活用されています。
天気図や気象情報の解析手法(Weather解析・AI活用含む)
解析手法の進化により、近年ではAIや機械学習を活用するケースが飛躍的に増えています。従来は気象庁のスーパーコンピュータによる数値予報モデルや気象衛星の観測データを中心に解析が行われていましたが、現在では膨大な過去データを学習したAIが短時間で予測を行う手法も導入されています。これにより、従来の数値モデルでは苦手だったゲリラ豪雨や局地的な突風なども、より高精度に予測できるようになってきました。
日本気象協会は公式サイト「tenki.jp」などで独自の気象解析を公開しており、短期的な予測だけでなく1か月予報や季節予報にもAIや統計解析を積極的に活用しています。
たとえばレジャーやアウトドア用に特化した天気図や、行動用途に応じた指数情報(洗濯・傘・紫外線・熱中症リスクなど)を分かりやすく表示するなど、生活者が実際に行動を決める際に役立つ形式で提供されています。
さらに、近年ではクラウドベースの解析プラットフォームを活用して、利用者から寄せられる観測データやIoT機器からの情報も解析に組み込み、従来よりもきめ細かい地域単位の天気予測が可能となっています。
天気予報の精度に違いはある?

天気予報の精度は「どの情報源を選ぶか」によって体感が大きく異なることがあります。気象庁は全国規模で均一なデータを提供するため信頼性が高く、特に災害時には欠かせない存在です。
一方で日本気象協会や民間気象会社は地域ごとの特徴や生活者の行動に役立つ形で情報を加工しているため、日常生活の利便性や体感的な「当たりやすさ」に優れています。これらの違いを理解することで、利用シーンに応じた賢い選択が可能になります。
「当たらない」と言われる背景と予報精度の仕組み
天気予報が「当たらない」と言われる背景には、地域ごとに急変する気象条件や、確率を伴う予測手法に対する理解不足があります。たとえば「降水確率50%」は、半分の確率で雨が降るという意味ではなく、同じ条件のもとで10回予測したら5回は雨が降る可能性があることを示す指標です。
このように、確率表現を誤解してしまうことで「外れた」と感じやすくなります。さらに、日本の気象は山岳や海洋の影響を受けやすく、短時間で天候が変わるため、どうしても局地的な誤差が生じやすいのです。予報は必ずしも”当たる・外れる”の二択ではなく、精度の分布や信頼区間を考慮して判断する必要があります。
また、天気予報の精度は時間スケールによっても異なります。数時間先の「短時間予報」は比較的正確ですが、1週間先の「週間予報」では誤差が大きくなります。予報の仕組みを理解したうえで活用すれば、「当たらない」との不満は軽減され、より適切に行動計画に生かすことができます。
日本気象協会天気予報の特徴・ランキングや口コミ
日本気象協会はユーザーフレンドリーな表現や、生活密着型の情報(洗濯指数、紫外線指数、熱中症予防指数など)に強みがあり、アプリ「tenki.jp」は高評価を受けています。
リアルタイム性や地域別の詳細表示に加え、グラフや図解で直感的にわかりやすく示される点も利用者から好評です。口コミでも「洗濯のタイミングが分かりやすい」「旅行前に確認すると安心できる」といった実用的なメリットが多く挙げられています。
気象庁予報の長所・短所と他社比較
気象庁の予報は厳格で中立性が高く、特に警報・注意報などの公式情報に基づいて行動が求められる防災の場面では最も信頼性があります。情報は慎重に発表され、過度に楽観的な予測や誇張を避けるため、公共的な立場から見ても揺るぎない安心感があります。
しかしその反面、生活者が知りたい「洗濯物が乾くか」「外出時に傘を持つべきか」といった具体的で実用的な情報はやや不足している傾向にあります。また、Webサイトの見やすさやアプリ機能の使いやすさなど、利便性や視認性の面では民間企業に後れを取る場面も指摘されています。
一方、民間企業や日本気象協会の予報は生活に直結する形で表現が工夫され、利用者にとって分かりやすく活用しやすいのが強みです。ただし、民間の場合は速報性や更新頻度を重視するあまり、予測の振れ幅が大きくなることもあり、安定性では気象庁に劣る場合があります。
したがって、防災を目的とする場合は気象庁、日常生活に即した判断には日本気象協会や民間企業と、シーンごとに使い分けるのが現実的といえるでしょう。
精度向上のための最新技術やシステムの活用
AIによる気象解析や、スーパーコンピュータ「富岳」などの活用により、天気予報の精度は年々向上しています。特に富岳を用いた数値予報モデルは、台風進路の予測やゲリラ豪雨の発生予測に大きな効果を上げています。
民間企業では独自の解析エンジンやAIアルゴリズムを持つところも多く、地域特化や短時間予報に特化した技術が進展しています。たとえば、数分単位の降雨予測や位置情報に基づくピンポイント通知など、利用者の生活に直結する新技術が積極的に導入されています。
今後は気象庁と民間双方の強みを掛け合わせることで、さらに高精度で利用者本位の予報が期待されます。
天気予報の発表・提供サービスの違い
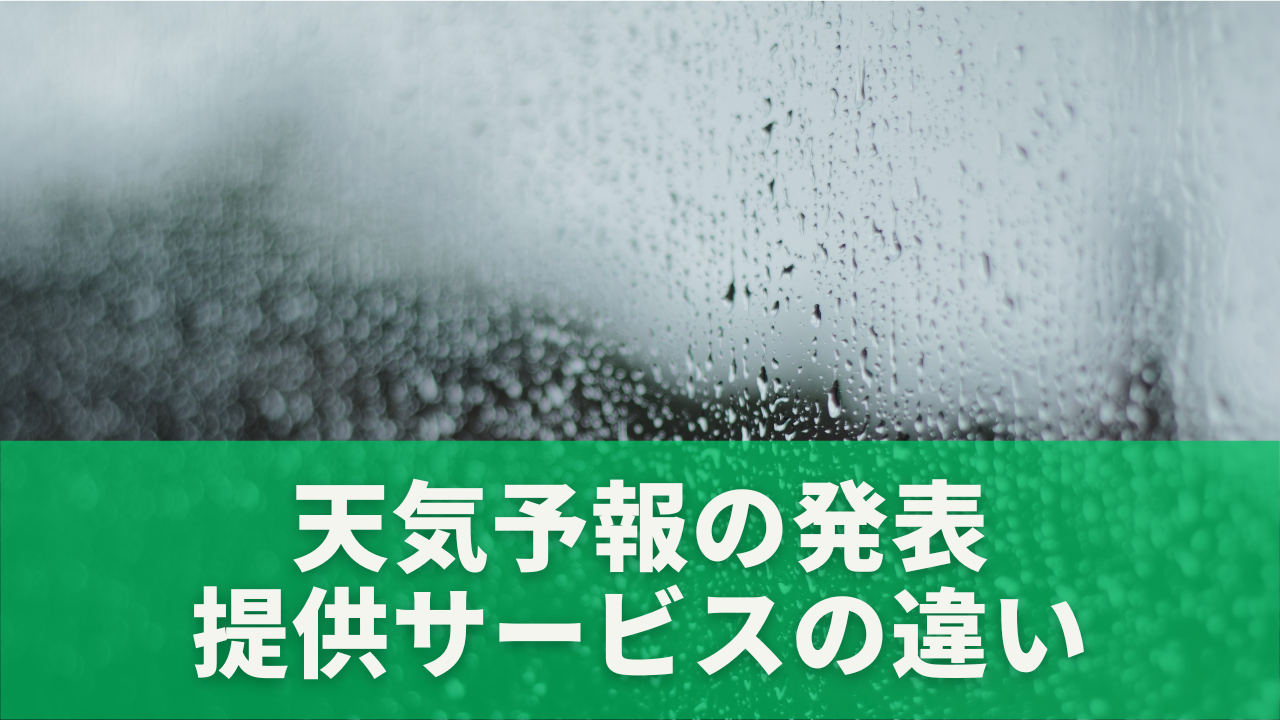
天気予報は単に「当たるか外れるか」だけではなく、その発表の仕方や提供されるサービスの種類によっても利用者の体験は大きく変わります。
気象庁は防災を最優先に据え、厳格で統一的な情報発信を基本としていますが、民間企業や日本気象協会は利用者の生活に役立つ多様なサービスや使いやすいインターフェースを展開しています。
ここでは、発表タイミング、更新頻度、情報提供の手段やコンテンツの違いを具体的に比較していきます。
発表タイミングと更新時間の比較
気象庁は1日4回(5時・11時・17時・23時)の更新が基本であり、災害時など特別な場合を除けば更新頻度は比較的少なめです。そのため、防災上の重要な情報には強い信頼性がある一方、短時間で急変する気象に即応するにはタイムラグが生じる場合もあります。
日本気象協会やウェザーニューズなどの民間予報はそれよりも更新頻度が高く、数時間おき、あるいは必要に応じてほぼリアルタイムでデータが更新されます。
特にゲリラ豪雨や局地的な雷雨といった現象に対しては、民間の速報性が利用者にとって大きなメリットとなります。利用者は「安定性重視の気象庁」「速報性や利便性に強みを持つ民間」といった特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが求められます。
アプリ・Webサイト・メールなどサービスの種類
日本気象協会の「tenki.jp」やウェザーニューズの「Weathernewsアプリ」では、Push通知やメール配信、カレンダー連携、地域ごとの細分化されたお天気マップなど、多彩な手段で情報提供が可能です。
さらに、ユーザー参加型で観測情報を共有する機能や、行動指数(洗濯・紫外線・熱中症など)の自動通知も備わっています。
気象庁は公式サイトや防災専用アプリ「キキクル」を通じて情報を提供しており、特に防災情報の正確性や信頼性に重点を置いています。
これらの違いを踏まえると、気象庁は公的で信頼性の高い基盤を提供し、民間は利便性とユーザー体験を重視する補完的な役割を果たしているといえます。
レジャー・防災情報・熱中症指数など提供コンテンツの違い
民間気象サービスは、花粉情報や熱中症指数、レジャー指数など「行動に結びつく情報」が豊富に揃っています。
加えて、洗濯指数、紫外線指数、風邪ひき指数といった日常生活に密着した便利なデータも提供され、ユーザーは毎日の行動判断に役立てることができます。
特に夏場の熱中症予防や春先の花粉症対策、冬場のインフルエンザ流行期など、季節ごとの生活リスクに対応した情報が重宝されます。
一方、気象庁は防災情報を中心に、正確性と信頼性を最優先にした発信を行っています。大雨特別警報や津波警報など、命に直結する情報の発表に重点が置かれ、社会全体の安全を守る役割を担っています。
スポット・地域ごとのピンポイント情報とその活用方法
民間気象会社は、町丁目レベルのピンポイント予報が可能なサービスを展開しており、旅行や野外イベント、スポーツ大会などで大きな力を発揮します。
近年では数百メートル単位での降雨予測や1時間先の雷雨予想など、短時間・狭エリアの情報精度も高まっています。これにより、ユーザーは自宅周辺や目的地の気象条件を事前に把握し、計画を柔軟に調整することができます。
気象庁の情報は市町村単位が基本であり、防災上の意思決定や広域的な判断に最適化されています。したがって、災害対応や避難判断には気象庁情報を、生活行動やレジャー計画には民間情報を活用するという併用スタイルが理想的です。
気象予報士・組織体制

気象予報士の仕事・採用(日本気象協会・気象庁・他民間)
気象予報士は国家資格で、取得には難関試験を突破する必要があり、理学・数学・物理の知識が求められます。
資格を取得した予報士は、気象庁の職員として数値解析や警報発表に携わったり、日本気象協会の職員として生活密着型情報を発信したり、テレビ局に所属して気象キャスターとして活躍したりと、多様なキャリアパスがあります。
年収面では、安定性を重視するなら気象庁勤務、幅広い経験やメディア露出を重視するなら協会や民間企業といった選択肢があり、個人の志向に応じた働き方が可能です。
日本気象協会の支社・組織構成
日本気象協会は全国に支社を持ち、各地域に根ざした気象サービスを展開しています。自治体・企業向けの気象コンサル業務や防災支援を担い、観光地やイベントの運営にも関与しています。
組織としては非営利法人であり、利益追求よりも公共性を重視し、情報発信以外にも教育・研究活動に力を入れています。たとえば気象教室や講演会、子ども向けの教育プログラムなどを通じて、気象リテラシーの普及にも努めています。
業務内容や民間・国の役割の違い
気象庁は防災・公共インフラに関わる情報を発信する使命があり、台風進路予想や地震速報など国民の安全を直接守る活動に特化しています。
一方で日本気象協会は、気象庁の基礎データを活用しつつ、それを市民生活や産業活動に役立つ形で加工・提供しています。たとえば花粉情報や熱中症指数などは協会独自の強みです。
また、民間気象会社は収益モデルを伴い、ユーザー体験や企業ニーズに応じた高度なサービスを展開しています。
こうした役割分担によって、国・非営利組織・民間がそれぞれの強みを活かし、日本全体の気象サービスが支えられているのです。
より正確な天気予報を選ぶコツと活用シーン

天気予報は一つの情報源だけを参照するよりも、目的や状況に応じて複数の予報を組み合わせることで、より高い精度と安心感を得ることができます。
災害対策、レジャー、健康管理など、目的ごとに最適な予報を選び分けることが重要です。ここでは、具体的な使い分けの考え方や、精度を高めるための工夫を詳しく紹介します。
目的別(災害・レジャー・季節行事など)の使い分けポイント
- 防災・災害対策:気象庁の公式発表が最優先です。特別警報や注意報は行政や自治体の避難勧告と直結しているため、命を守る行動に直結します。最新の警報や危険度分布をチェックすることで、より的確な判断が可能になります。
- アウトドア・旅行・イベント:日本気象協会やウェザーニューズのピンポイント情報が役立ちます。数百メートル単位での局地的な降雨予測や、1時間ごとの詳細な気温変化などを確認することで、旅行計画やレジャーイベントを柔軟に調整することができます。口コミ評価や実際の過去データを組み合わせれば、さらに信頼度が高まります。
- 健康管理・洗濯・通勤:指数系情報が豊富な民間サービスが便利です。洗濯指数、紫外線指数、花粉情報、熱中症指数など、日常の行動に直結する情報が整理されており、忙しい朝の判断を大幅にサポートします。通勤通学時の急な雨を避けたり、健康リスクを予防するうえでも役立ちます。さらに、季節行事や農作業など特定の活動に合わせて情報を選ぶことも有効です。
防災・災害対策で注目すべき情報
「キキクル(危険度分布)」「警報・注意報」「特別警報」など、気象庁が発表する防災関連情報は、正確に把握し、自治体の避難情報とあわせて活用しましょう。
特にキキクルは、雨量や河川水位、土砂災害の危険度を色分けで直感的に示してくれるため、一般の利用者でも危険度を一目で判断しやすいツールです。
また、警報や特別警報は、自治体からの避難指示や学校の休校判断などに直結する重要な情報であり、命を守る行動につながります。
さらに、気象庁以外の民間サービスも補完的に利用することで、より多角的な判断が可能になります。例えば日本気象協会が提供する地域ごとの危険度マップや、ウェザーニューズのリアルタイム報告機能などを組み合わせれば、状況を多面的に把握できます。
自宅周辺だけでなく通勤・通学路、旅行先や実家など複数の地域の情報を同時にチェックする習慣を持つことで、予期せぬリスクにも備えられます。
ランキングや過去データを活用した賢い選び方
各サービスが発表する「予報精度ランキング」や「当たりやすい時間帯」「地点別過去データ」なども参考にすると、用途に応じた使い分けが可能になります。
例えば、ある地域でどのサービスの予報が過去に最も的中していたかをランキング形式で確認すれば、自分の住んでいるエリアや行動範囲に合った予報元を選ぶことができます。
また、降水確率が高い時間帯や気温のピーク時間を過去データから把握することで、通勤や外出の計画をより合理的に立てられます。
さらに、農業やイベント運営などでは長期的な過去データを参考にすることで、気候傾向を踏まえた準備や対策も可能になります。
複数のサービスを比較し、信頼性の高いものを選択する姿勢が、結果的に最も賢い天気予報の活用法につながります。
よくある質問・最新情報まとめ(気象庁・日本気象協会Q&A)
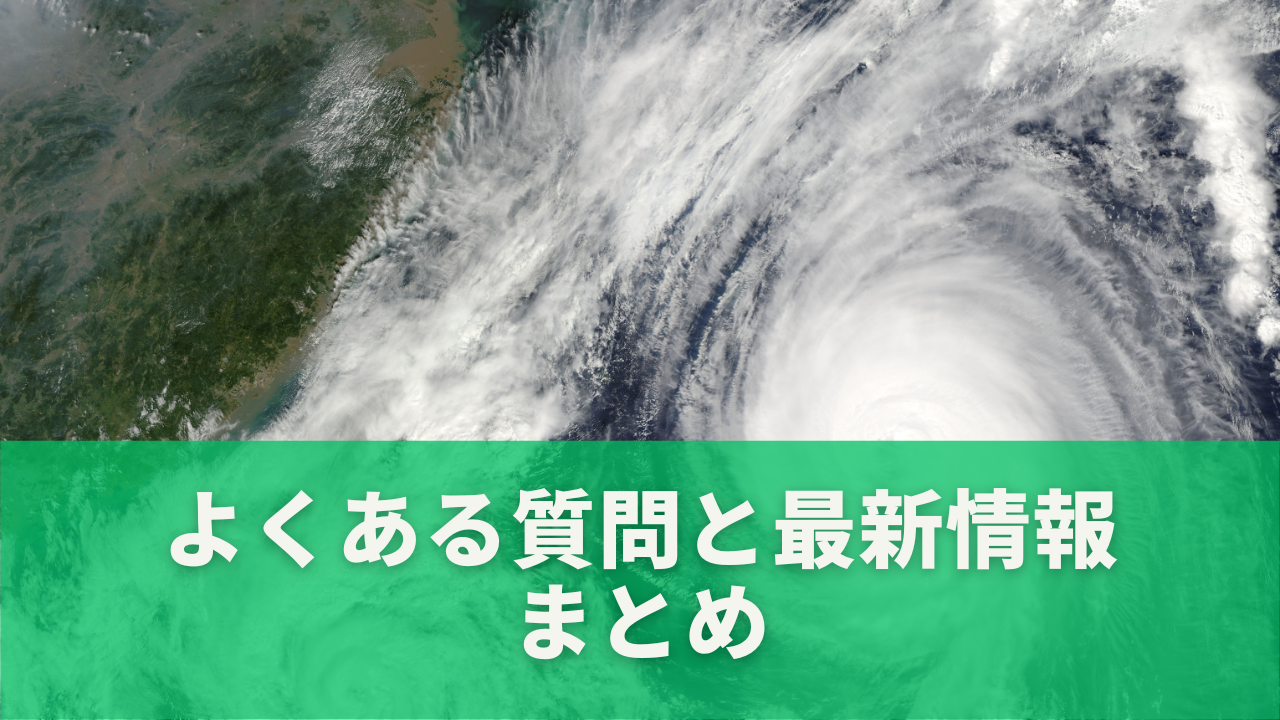
このセクションでは、利用者からよく寄せられる疑問や最新のサービス情報をまとめています。
気象庁と日本気象協会の公式ページやアプリの活用方法、サービス終了に関する注意点、さらには今後の気象予報の技術進化や国際的な動向など、実用的かつ最新の情報を整理しました。
Q&A形式で確認できるようにしておくと、日常生活や災害時に素早く必要な情報にアクセスできる利点があります。
各種公式情報・URL・アプリのまとめ
- 気象庁:https://www.jma.go.jp/
- 日本気象協会:https://www.jwa.or.jp/
- tenki.jp:https://tenki.jp/
- キキクル:https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=default&area_type=offices&area_code=130000
終了したサービスや変更に関する注意点
過去には一部のアプリや情報提供サービスが終了したケースもあります。たとえば、スマホ向けの旧型天気アプリやテレビ連動型の地域限定サービスが提供を終えたことがあり、利用者が突然情報を得られなくなる事例も見られました。
また、サービス内容の刷新や名称変更により、以前使っていた機能が新しい形に統合されるケースもあります。したがって、利用しているサービスが今後も継続されるか、どのような更新スケジュールを持っているかを常にチェックすることが重要です。
最新のサービス提供状況や更新頻度、終了予定などは、各公式サイトで必ず確認しておくと安心です。
今後の天気予報の進化と世界的動向
AI・ビッグデータ解析の進化により、天気予報はますます高精度化・個別最適化が進むとされています。これまでの数値モデル中心の解析に加えて、機械学習や深層学習を取り入れることで、従来では予測が難しかったゲリラ豪雨や突風などの短時間現象にも対応できるようになりつつあります。
世界的にもモバイル特化型予報やパーソナライズド通知が注目されており、日本でも同様の流れが加速しています。例えば海外では、利用者の位置情報や行動履歴に合わせて「数分後に自宅周辺で雨が降る可能性が高い」といった超短時間予報を通知するサービスが普及し始めています。
今後はスマート家電やウェアラブル端末と連携したパーソナル天気予報の仕組みが一般化することが期待されます。エアコンが外気温や湿度の予測をもとに自動調整したり、スマートウォッチが紫外線指数や熱中症リスクをリアルタイムで警告したりするような機能が、生活に自然に組み込まれていくでしょう。
さらに、地域の細分化に基づいたリアルタイム警戒システムの開発も進んでおり、自治体や防災機関が即時に避難判断を下せる環境が整いつつあります。将来的には、AIが個々のライフスタイルや住環境を学習し、必要なタイミングで最適な気象情報を届ける“パーソナル気象アシスタント”のような存在が一般化する可能性もあり、生活のあらゆるシーンで天気情報が自動的に活用される時代が到来すると考えられます。
まとめ

- 防災や災害対応には、気象庁の公式発表が最も信頼できる。
- 日常生活やレジャーには、日本気象協会のわかりやすい情報が便利。
- 民間企業は速報性や独自サービスで差別化し、ユーザー体験を向上させている。
- 目的やシーンに応じて、複数の予報を組み合わせて活用するのが理想的。
- 最新技術の活用により、今後も予報精度や利便性はさらに向上していく。
- 国の防災インフラを担う気象庁、生活情報に強い日本気象協会、そして先進技術で差別化を図る民間企業が互いに補完し合うことで、日本の天気予報は成り立っている。
- 利用者は自分の目的に合わせて情報を取捨選択することで、最も効率的かつ安心な生活を送れる。
天気予報は一元的に「どちらが正確か」を問うのではなく、それぞれの強みを理解し、シーンに応じて使い分けることで最大限に活用できます。
気象庁は公的な信頼性、協会や民間は生活者目線の利便性という特徴を持っており、両者を補完的に利用することが、安心で快適な生活につながります。
さらに、最新技術やAIの発展により、天気予報はますます精緻で身近な存在へと進化し続けています。私たちが正しく情報を活用すれば、日常の計画から命を守る行動まで、天気予報はかけがえのないパートナーであり続けるでしょう。